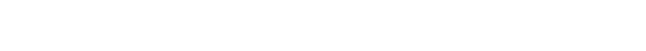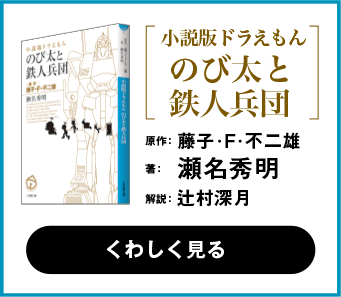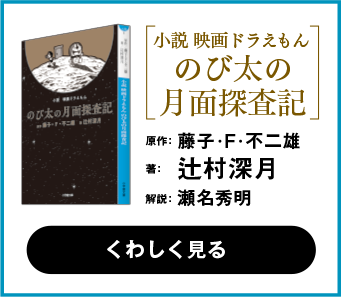パピやドラコルルの人間性を深く描いているところなど、映画で新しく加わったどの要素も、決して原作を大きく変えているわけではありません。ちょっとしたセリフで奥行きを与えているんですよね。そこが素晴らしいと思いました。
全体的にお話の展開やキャラクターの気持ちを、説明しすぎないところがいいですね。映画を作っている人たちが、見ている子どもたちを信頼しているからでしょう。
スネ夫の脱げたくつがポツンと映し出される場面なんかもそうですが、アニメやまんがって「絵を読む」ことなんだとあらためて感じました。藤子先生の作品をはじめ、たくさんのアニメやまんがが表現を切り開いてきた歴史があって、きっと私たちもこうして絵を読むことができるんだなと、今回の映画を見て再確認できた気がします。
スネ夫といえば、今回はとくに印象に残る場面が多かった。ラジコンの改造で大活躍するスネ夫ですが、一方で戦いが恐くて隠れてしまうという弱さもしっかり描かれている。そのおかげでぼくは、ものすごくスネ夫に感情移入できました。また、スネ夫の弱さがあるから、対象的にしずかちゃんの強さも際立つんですね。

そう、しずかちゃんのかっこよさ! 「このまま負けちゃうなんて、あんまりみじめじゃない!」って、戦闘機の大群に向かっていく場面。あそこが私のイチ推しシーンです。いまは世界中のいろいろな映画で、女の子の活躍もたくさん描かれるようになっていますが、私が子どものころから藤子先生はそれを描いていたんだっていうことにあらためて気がつき、本当に感激しました。

いまの時代だから描いているのではなく、しずかちゃんならきっとそうするだろうと、見ている人も納得できるんですよね。そもそも彼女を、そういう性格に設定した藤子先生が素晴らしいなと思いますね。
社会の分断や人々の連帯というテーマに加え、女の子であるしずかちゃんの活躍シーンも光る、とても現代的な映画ですが、実はすべて藤子先生の原作に描かれていることなんですよね。ドラえもんには、どの時代にも通じる普遍性がきちんと描かれているのだと感動します。